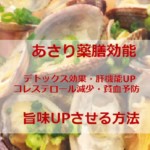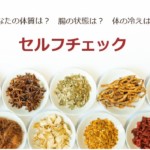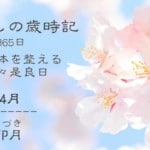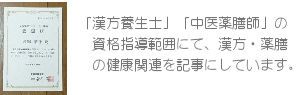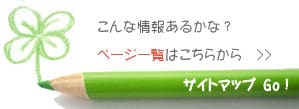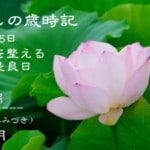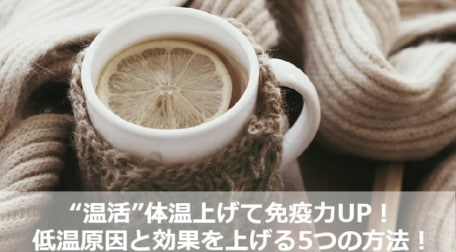しかし難しいこともなく、早寝早起き・寒い時は体を温め、暑い時は体を冷まし、イライラしたらリラックスができるようにする…という、あなたが自然に行っていることもあると思います。
「養生」は病気を治すというよりも、健康的な体を作ろうと考え、本来もっている生命力を最大限に引き出すように過ごす手段です。
日本には四季があり、それぞれの季節の気候は大きく変化していきますが、私たちはそれに適応しながら健康を維持しています。
季節の合わせて病気にならないようにするには、それぞれの季節に合った「養生」が必要です。
バランスのとれた食事・適度な運動と休養・心のケアと、無理をしないで自然と調和して暮らせるように、四季別により気を付けると良い特徴を綴っています。
Contents
冬の養生法:注意すべき生活と食養生
日差しが弱まって寒さに耐える冬ですね。
自然界の植物や動物たちは、自然の流れに従って、冬眠したりとひっそりと静かに生きています。
漢方では活気あふれる春を迎えられるように、冬は「エネルギーを蓄える季節」と考えています。
ギラギラした夏を過ごし、秋では冬の蓄えのために、おいしい旬の食べ物が多く、冬ではできるだけ気力や体力を消耗しないように過ごしていきます。
冬の養生ポイント:気力・体力を備える
寒さと乾燥で免疫力が低下する冬。
一年で不調になりやすい時期でもあります。
冬の体力や免疫力を維持するためにも、冬では五臓の「腎」がエネルギーを蓄える働きをしてくれています。
「腎」は生命活動に重要な精気を蓄えている五臓についての関連記事。
冬になるとトイレが近くなりませんか?
それは、寒さで汗が少ない冬で、不要な水分を尿として排出させているのですが、その働きをするのが「腎」で、水分代謝を司る働きがあります。
「腎」に負担がかかると、水分が上手に排出されないため、体や顔が浮腫んだり、泌尿器系のトラブルを起こしやすくなります。
疲れた「腎」を守るために、食事と入浴・衣類などで寒さ対策をしっかり行うことが大切です。
冬は、気力と体力を体に蓄えるように心がけ、春を迎えられるようにしましょう。
冬の養生ポイント:体を冷やさないように気を付ける

冬に限らず体を冷やさないようにするのは、年間通して必要です。
特に体の芯から冷やしてしまう冬は要注意。
温かい食べ物は、冬では体が求めると思いますが、ファッションを優先してしまい、衣類に気を付けることを怠りがちになります。
衣類を上手に調整すべき部位は、首・腰・足元です。
「腎」のある腰は、必ず温かい衣類を身に着けて冷やさないようにしましょう。
そして、室内温度にも注意です。
汗をかくほどの暖房によってかく汗は、運動をしてかく汗とは違います。
冬なのに室内温度が高く汗をかくと、冬の間に蓄えておきたいエネルギーが汗とともに、いっしょに出てしまいます。
その上、外との激しい気温差が体に大きな負担をかけてしまうので、室内温度には気を付けるようにしましょう。
冬の養生ポイント:睡眠時間を意識してたっぷりと!

運動や仕事をすることだけが体力を消耗してしまうことではありません。
寒さも体力を消耗してしまうので、冬は他の動物と同様に睡眠をしっかりとる必要があります。
睡眠で疲れた体を休めるためにも、冬は早めに寝ることをおすすめします。
そして、寒い冬では太陽がのぼる前は、体を冷やす時間になってしまうので、朝日がのぼってから起きるという習慣を意識してください。
寒い冬なので、布団の中でぬくぬくしていたいと思うので、わざわざ朝日がのぼる前に起きる人は少ないと思いますが、少しでも体を冷やさないように意識して行動しましょう。
冬の備えのための食事を意識:食べたい食材と冬の薬膳

冬の寒さの栄養を受けやすいのが、五臓の「腎」です。
その「腎」を助ける食材は、体を温める旬の食べ物に多く含まれていますが、特に黒い食材に弱った「腎」を元気にしてくれる働きがあります。
とにかく冬は体を温めることを第一に考えて食べるようにしましょう。
羊肉が体を温める食材としてあげられますが、なかなか気軽に入手し食べられる食材ではありませんね。
体をあたためる代表的な食材は、鶏肉・えび・長ネギ・玉ネギ・かぼちゃ・にら・くるみ・シナモン・とうがらし・八角・熱した生姜などです。
弱った「腎」を元気にする食材は、黒きくらげや黒ゴマ・黒豆などの黒い食材で、血を増やし血行を良くして体を温めてくれます。
免疫力をアップさせるためには、きのこ類がおすすめ!
そして、冬の風邪の予防として、気軽にビタミン補給ができる柑橘類のみかんが市場に多く出回ります。
不足してしまいそうな野菜は、体を温める鍋料理に使われる食材で補えます。
具体的な旬の食材は次のページで紹介します。
↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日