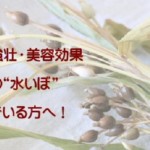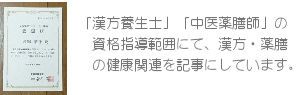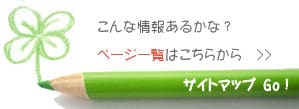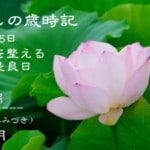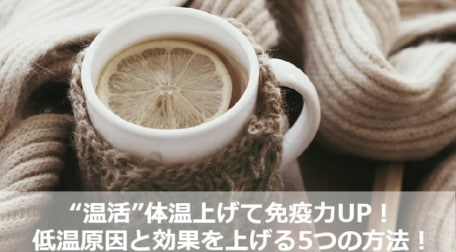人は外界であらゆる気を使って生きています。
元気が失われないように、元気をおぎなう食事をいただき、呼吸を深くして、質のよい睡眠をとる…これは健康を維持していく基本でもあります。
大切な人のために…自分の健康管理のために、旬の食べ物・食べ合わせなど、わざわざ薬膳のために食材を購入しなくても、食べ方や料理方法で「薬膳」になります。
Contents
体の不調はいつ感じるのか?…薬膳の目的は?
薬膳の目的は、病気を予防することと、不調が現れた時にどう食べて改善していくかの2つです。
日常の出来事によって体調不良になる場合もありますが、東洋医学では「自然界が体にも影響する」と考えられています。
旬の食べ物を積極的に取り入れることで、十分な効能が期待されることから、薬膳を意識する方が増えてきました。
四季の気候と起こりがちな不調は?
美しい日本の四季ですが、湿気が多いことや乾燥している季節や、季節の変わり目の温度差で体調不良になる原因が様々です。
その四季に応じて、自然界ではその変化に耐えられるような植物が多く、その恵みを上手に生かして食べるのが“食養生”。
そして、季節の他にも土地によっても四季の差があるため、地産地消(地域で生産された様々な生産物や資源)の食材をいただくことも“健康”への道でもあります。
治療も兼ねた薬膳では意識して食べた方がよいものなどは取り寄せなければならないものがあるかもしれませんが、健康維持を目的とした食事であるならば、旬に応じた地域で作られている野菜を食べることが風土と自分の体が合っているとも言えます。
四季ごとの体調不良を前もって意識することで、様々なトラブルを回避できるので、ぜひ食生活に取り入れてください。
四季特有の不調を予め予防して、心地よく生活ができるようにする食事が「薬膳」です。
春の食養生

万物が芽生える春。
陽気が高まって心身の働きが活発になりますが、「肝」である自律神経が過剰に働くので、心と体のバランスが崩れ自律神経失調症などの症状が現れやすくなります。
そして、春は吹く風によって不調が起こりやすく、風邪・花粉症・イライラ・めまい・気が撹乱しやすいと言われています。
血を養い、気の巡りをよくする作用の食物によって、「肝」の機能を正常に戻す食養生が基本になります。
春の食養生のページで、おすすめの食材など、春の対策が詳しく書かれています。
夏の食養生

蒸し暑い日本の夏。
日々の暑さによって、血流に問題・気力が消耗しやすく、多汗・貧血・炎症・不眠・イライラなどの症状があります。
体に余分な熱がたまり、水分の調整が難しいため熱中症になったり、利用作用が弱り水分のとりすぎでむくみやすくなり、食欲がなく、だるくてやる気がでないなどの夏バテの症状が出ます。
日本の夏と上手に付き合うには清熱利尿(せいねつりにょう)の作用があるものを食べる食養生が必要です。
秋の食養生

空気が乾燥して植物が枯れる秋。
人の体も同じように潤いがなくなり、空気の乾燥によって、肺や皮膚に不調が出やすく、咳・鼻炎・湿疹・皮膚のかゆみ・アレルギーなどに注意する必要があります。
まず「肺」に潤いが与え、体の乾燥を防ぐはたらきがある食べ物を意識して食べましょう。
冬の食養生

植物が新陳代謝を最小限に抑えて、栄養分を幹や根に蓄えられるように生きている冬。
人も新陳代謝が下がり、栄養分を体内に蓄えていく季節です。
冬は寒さによって排尿・血流に不調がでやすく、冷え性・頻尿・耳鳴り・腰痛・膀胱炎などの症状がでやすいため、体を温めて血行を促し、元気を蓄える食養生になります。
食べ方を見直そう!-基本の食べ方
お腹を元気にする食べ方は、薬膳に限ったことではありません。
基本的な食べ方を心がけましょう!
- よく噛む
一口30回が健康的な食べ方ですが、早食いの方は難しいことですが、1ヶ月を目標に徐々に噛むことに気をつけていきましょう。 - 腹八分目を心がける
満腹は風船のように胃が膨らんでしまう状態なので、粘膜が薄くなって消化が落ちてしまうので、意識しながら食べるようにしましょう。 - 冷飲冷食を避ける
冷たいものが胃の中の入ることで、消化と体温を上げようとするエネルギーが必要になり、疲労感に悩まされることになります。 - 甘いものを食べすぎない
疲れた時に甘いものを欲するのは体が疲れているからですが、ダラダラ食べるのは肝臓の負担・排尿の妨げ・むくみの原因になります。 - 揚げ物は控えめにする
高カロリーの食べ物は消化するのに時間がかかり、胃腸が弱っている人は消化不良になって、エネルギーが蓄積されるのことで、肥満・血行不良の原因となります。
病気を予防するためにも、食べ方は基本中の基本として注意するようにしましょう。
そして、薬膳は体に優しい食事を摂ることが基本ですし、日常で食べている野菜類なども十分な薬膳の食材です。
煮たり蒸したりするのが、体にやさしい調理方法です。
身近な食材で、薬膳を意識した料理を紹介して参ります。
↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日