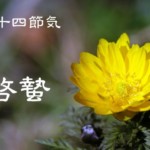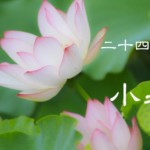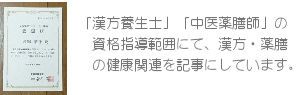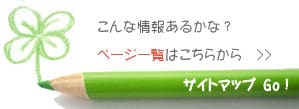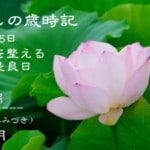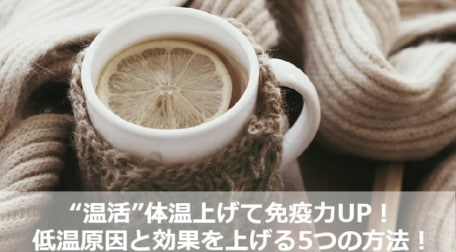Contents
季節の最盛期の食べ物「旬のもの」
 「旬のもの」とは、季節の最盛期の食べ物の意味です。
「旬のもの」とは、季節の最盛期の食べ物の意味です。
日本には四季という美しい景色の中に、季節折々、旬の食事を楽しめる素敵な食文化がありますね。
旬のものは、味がしっかりあり量もたくさん取れて、四季の大地のエネルギーをたっぷり含んでいるので、栄養成分も申し分ありません。
自然摂理であるリズムに沿って、食物を体に入れることが生命力を高める食べ方なので、毎日のようにTVであれがいい!これがいい!と情報に振り回される前に、基本を理解した上で良い物を取り入れませんか?
しかし、技術が発展し四季を問わずに店頭にはさまざまな食材が並んでいるため、何が旬なのか?体は何を欲しているのか?ということを考える機会がなくなり、寒い冬に夏の野菜を食べて体を冷やしてしまうような毎日を過ごしているのです。
四季ごとに生み出す大地のエネルギーいっぱいの食べ物には、その時期に体を整えるために必要な成分が実に巧妙に分配されているのです。
春は苦味、夏は酸味、秋は甘み、冬は厚味…とされています。
「四季の食養生」旬のものの栄養は、体を整えるにあたり理にかなっている
旬の果物や野菜などに含まれる栄養素の特徴として、草木が芽生えるとき、急速に細胞分裂する眼の部分に大量にビタミンCが発生します。
旬の食べ物には生命力にあふれ、人間の生命を維持するための重要な代謝酵素や消化酵素などのさまざまな酵素が豊富に含まれているのです。
春の養生 …(苦味)紫外線に備えることができる

海藻には紫外線から体を守る抗酸化物質ポリフェノールが豊富に含まれているものが多く、春野菜や山菜など苦味のある食材をしっかり食べて紫外線対策ができます。
セロリ、キャベツ、いちご、わかめ、ホタテ、たけのこ、ふき、せりなどの山菜など
夏の養生…(酸味)水分不足に注意!渇いた体を潤せる

食欲不振を改善し、ほてりやむくみや夏バテに備え、食からもしっかり水分補給を行うことで、体の余分な熱を取って、汗で失う体液のバランスを補うものが多いため熱中症の予防にもなります。
アジ、イワシ、タコ、みょうが、枝豆、ピーマン、びわ、きゅうり、トマト、なすなど
秋の養生 …(甘み)夏の疲労回復と冬への備えができる

野生動物の冬眠のように、寒くなる前にエネルギーを蓄積する働きを担うい、自然の恵みをたくさん摂れる時期です。穀物やいも類、果物など甘味のある食材が多いですね。
くり、なし、かき、さつまいも、ごぼう、ぎんなん、落花生など
冬の養生…(厚味) 体を温める

冬野菜の白菜や大根は、食べ過ぎ、飲み過ぎたりして疲れた胃をいたわる効果がありますが、体を冷やすので鍋など温かい調理にしてたべる料理方法が多いです。脂がのった魚や根菜類など体を温める旬のものが出回りますね。
マグロ、タラ、ねぎ、ほうれん草、ゆり根、かぶ、白菜、大根、くるみ、きんかんなど
「旬の初物を食べると長生きする」という言葉があるように、活発な酵素や豊富なビタミン、ミネラルを季節ごとに食べるように心がけるようにしてから、健康情報を上手に取り入れていきましょう。
↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日