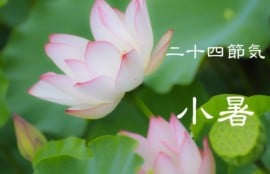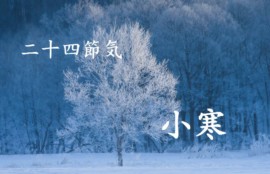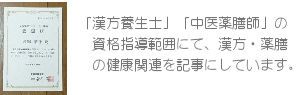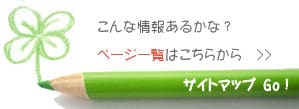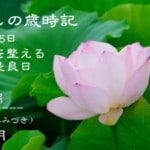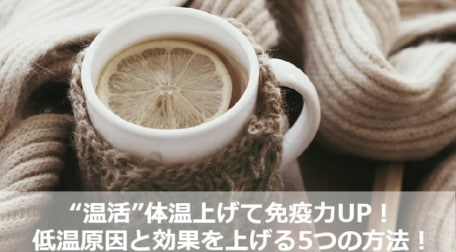6月は「水無月」といい、田植えも終わり水を張る月という「水張り月」・農作業をし尽くしたという「皆尽月」・水も涸れる尽きる「水無月」など、いずれも“水”との関係が関わり、梅雨や農業の終わりを表現しています。
Contents
二十四節気の夏【夏至-げし】6/21~7/6頃
この頃に紫の花穂だった「夏枯草」は、枯れはじめて黒ずみ始め、薬膳ではこの夏枯草を薬草と煎じて体調を整えてたりします。
二十四節気の夏にあたる「夏至」は6/21~7/6頃で、梅雨の真っ盛りで、湿気が多い季節です。
日本人特有の“寂-さび”の精神は、雨の多い季節での鉄などが錆びる“錆の季節”があったからだとも言われています。
北半球では昼が最も長くて夜が最も短くなる時季で、空気も澱んで気分も憂鬱になって、食欲も衰えてしまうことが多いです。
夏至ではデトックスを心がけましょう

四季をバイオリズムで考えると月で言う「満月」で、最も陽気の盛んな頂点になっています。
体の錆をデトックスしていく時になります。
骨盤が最も歪む時季でもあるので、骨盤矯正のような調節もこの時期にはとても効果的です。
整体などに行くきっかけにしたり、自宅での調整する運動は、腰を時計回り→反対回り→八の字に回します。
骨盤回りには、直立歩行の基本になる仙骨があり、日常生活で腰には負担をかけているので、歪みやすい時季では意識して動かしましょう。
そして、食べ物だけでのデトックスではなく、呼吸法でも気の充実に効果があります。
鼻で吸って鼻で吐く・鼻で吸って口で吐く・口で吸って鼻で吐くなど、電車の中でも人に気づけれることなくできることですし、何気なく過ごしている時間でも腹式呼吸などをして呼吸を意識して“気”を高めたりすることで、血の滞りに繋がります。
この時期は、精神的に落ち込むことが多く、不眠にも注意が必要です。
夏至の体の管理と食生活
高血圧や心筋梗塞などの血管系の循環器病に要注意です。
血液の栄養と血管壁を丈夫にするような食生活を心掛けましょう。
食材として、血を増やすことに気をつける方が多いですが、血の流れを良くする食材にも注意するという、両方が必要です。
夏至の時季の薬膳「あずき」と「冬瓜」がおすすめ!

小豆は暑がりでも寒がりの両方の方に合う食材で、心穏やかにストレスが改善され、心臓にも良いとされています。
体の中の水分代謝をよくするので、尿や腫物を治し、むくみの改善・散血作用・充血などの解毒にもなるので、小豆粥などの料理をデトックス目的で食べるのが有効です。
京都の和菓子で水無月で食べる「水無月」があり、小豆が使われていて、昔からこの時季には小豆が健康に導くとされています。
近年まで京都でしか食べられていなかった生菓子「水無月」でした。
他には、「タコ」を食べる風習があり、田植えの根が八方に根をはって丈夫な作物に育つようにという願いと感謝の気持ちも含まれて、食べられています。
冬至では「かぼちゃ」を食べる風習がありますが、夏至に食べるものは「冬瓜とうがん」です。
冬瓜は「冬」という漢字が含まれているので、冬の食べ物に思われがちですが、夏野菜で、水分量が多くて体を冷やしてくれる野菜なので、夏至の頃の食欲不振や夏バテになりそうな体の調整をしてくれます。
栄養がないように感じますが、むくみ・高血圧。便秘などの予防ができることから、様々な効果を得ることができます。
部屋の湿気・食中毒など、環境が様々な影響を受けてしまう時期ですので、体に湿気やカビ・菌などを溜め込まないようにデトックスに気をつけましょう。
東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日