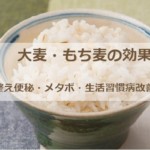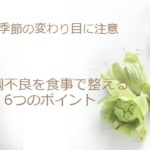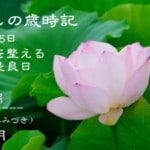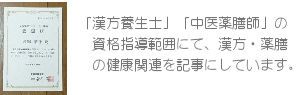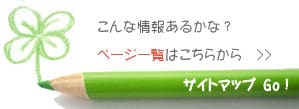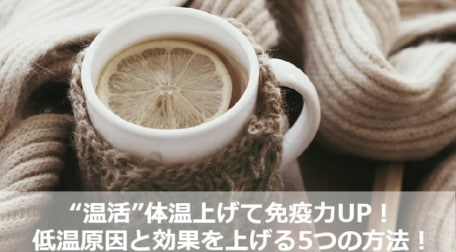杏(アプリコット)は、生食ができる種類もありますが、一年中市場に出ているのは、干したものやシロップ漬けが中心で、ジャムなどの加工品が多いです。
酸味が強い果物ですが、乾燥すると甘味が増すため、ドライフルーツとして売られているものは甘酸っぱくておやつになりますね。
その杏の薬膳としての効能は、アンズの実も種も漢方として薬効があります。
今回は、杏の実の栄養と効果効能をご紹介します。
Contents
杏(あんず)は実から種まで栄養が豊富

杏(アプリコット)は、中国が原産ですがヨーロッパに伝わり、18世紀ではアメリカで栽培されるようになり、現在は世界的な産地はカルフォルニア産になっています。
日本では青森県と長野県で生産されて、6~7月が旬で橙色の実が熟して市場に出される美味しい季節です。
街のスーパーではなかなか出会うことがないので、そのまま生食する機会がありませんが、見かけたら生食したり、干してドライフルーツ、ジャムやシロップを作りたいところです。
乾燥することで栄養が増え甘味が増すので、ドライフルーツが食べやすく一年中流通しているので、手軽に食べることができます。
杏(あんず・アプリコット)の栄養と効果効能

生の杏はすっぱいのですが、干すことで栄養が増えて、おやつになるほど甘くなっています。
生の杏と干した杏では栄養素の数値が変わっていきますが、はじめに杏の栄養から紹介します。
杏は冷え性や滋養強壮・エイジングケアと、女性に嬉しい栄養がたっぷりあります。
きれいなオレンジ色は「β-カロテン」で、栄養が凝縮されたドライフルーツあ栄養価が高く美容によいことから、正解のセレブの美容おやつとして愛用されています。
β-カロテン…抗酸化作用やアンチエイジング
杏の果肉に含まれるβ-カロテンは、人参や南瓜の野菜や他の果物よりも多く含まれています。
β-カロテンは体内に入ると、免疫力を高める働きがあるビタミンAへと変換されるので、風邪やインフルエンザ・感染症予防が期待できます。
新しい皮膚を作り出す働きがあるため、古い肌や汚れが付着した皮膚を、新しく変えてくれるため、美肌を維持する効果に期待され、アンチエイジングの栄養素と言われています。
抗酸化作用や粘膜の保護のためにも、ビタミンAは欠かせません。
食物繊維…腸内環境の働きを整える
食物繊維には腸内環境の働きを整える働きがあり、さらに毒素や老廃物も一緒に排出する効果があります。
腸内環境の働きが活性化することで、代謝がアップして便秘解消によって高いアンチエイジング効果が期待できます。
便秘は様々な病気を引き起こし、食物繊維はその便秘予防ができるため、生活習慣病(心筋梗塞、糖尿病、肥満など)の予防に役立ちます。
ほとんどの日本人が食物繊維不足であることから、積極的に食物繊維を摂取することが推奨されています。
カリウム…水分と塩分のバランスを整える
カリウムには、体内の水分量と塩分量を、バランスを取りながら維持調整(利尿作用や発汗)する働きがあるので、欠かせないミネラルのひとつです。
日本人は食塩(ナトリウム)の摂り過ぎと言われていますが、逆にカリウム不足であるとも考えられます。
ナトリウムの排出を促進するため、浮腫みや高血圧の予防として血圧上昇を抑制する働きがあるので、浮腫みや高血圧が気になる方にお勧めです。
鉄…冷え性や貧血予防
血液中のヘモグロビンの鉄は、酸素を体中に運んで、酸素を効率的に全身にいきわたらせる働きがあります。
その働きが怠ってしまうと、貧血や冷え性になるため、特に女性が必要な栄養素です。
杏には、血液を作り出すのに欠かせない鉄が豊富に含まれています。
そして、活性酸素を分解する働きもあるため、疲労回復にもつながります。
有機酸…殺菌作用と疲労回復
食べると酸っぱい杏の特徴である酸味の主成分は、有機酸(クエン酸・リンゴ酸など)です。
有機酸には、腸内にいるサルモネラ菌や大腸菌などの病原菌の殺菌作用があり、更に脂肪酸からエネルギーを作り出すことから、疲労回復の効果もあります。
有機酸は、日々の健康に関わるため重要な栄養素です。
ギャバ…脳の血行を良くする作用
脳の血行を良くする作用があるアミノ酸の一種のギャバは、杏の果肉にも含まれています。
脳動脈硬化症などのボケの予防や、脳の血行を良くする作用が知られていますので、学生さんにもお勧めです。
睡眠の質を高め、緊張やストレスなどを和らげ、脳の興奮を鎮める働きがあります。
干し杏(あんず・アプリコット)の効能効果

干し杏は、適度な甘みと酸味を感じ、そのまま食べても十分おいしいおやつになります。
甘みの成分はブドウ糖・果糖で、酸味の主成分はリンゴ酸、クエン酸などの有機酸です。
杏には体を温める作用があり、干しあんずを毎日数個食べ続けて冷え性が改善される場合がありますが、砂糖を加える加工品ではなく、純粋な干し杏の場合ですので注意が必要です。
生の杏でもビタミン類ではビタミンAが多く、ミネラル類も豊富に含まれていますが、特に干し杏にはミネラル類が多く含まれています。
| 杏の比較 | 生の杏 | 干し杏 | 比較 |
|---|---|---|---|
| β-カロテン(μg) | 1,400μg | 4,800μg | 3.4倍 |
| 食物繊維(g) | 1,6g | 9.6g | 6.1倍 |
| カリウム(㎎) | 200㎎ | 1,300㎎ | 6.5倍 |
| 鉄(㎎) | 0.3㎎ | 2.3㎎ | 7.6倍 |
生のあんずと干しあんずの栄養価を比較すると、干し杏の栄養価がアップすることが分かります。
薬膳では干し杏は、早い疲労回復剤として利用しますし、食べるとすぐに吸収されてエネルギーに変わるので、激しい運動をしたり仕事で疲れたときなどに、2~3個食べるだけで疲労が回復します。
薬膳としての効能としては、杏の実は体を温める性質があり、喉の渇きや切れにくい痰にも良く、内臓の機能低下や発熱による腫れを抑える効果を生かし料理します。
杏の種の杏仁も、肺に潤いを与え乾いた喉を潤し、整腸効果がありるので、生薬として咳止めや痰を抑える効果を生かして料理します。
デザートでよくいただく「杏仁豆腐」に使用される杏の種に含まれている“アミグダリン”は、咳止め作用があるといわれることから、漢方薬として使用されていますし、家庭内で気軽につくれるデザートメニューにもなっていますが、杏は漢方の処方箋にも用いられている生薬です。
干し杏は多くの栄養素をアップさせていますが、糖分量も増えるので1日2~3個程が適量で、体によいからと、多く食べる物ではありません。
干し杏(あんず・アプリコット)の食べ方と選び方
ドライフルーツとして「アプリコット」として販売されている「干し杏」の食べ方や選び方を紹介します。
干し杏の食べ方

杏はそのまま食べても十分甘酸っぱくおいしいですが、パンやケーキなどで味も栄養も凝縮された干し杏を加えるととてもおいしくできあがります。
昔ながらの「あんみつ」では、干し杏がトッピングされていますね。
私は餡はもちろんのこと、もちもちした求肥と杏のトッピングが好きです。
そして、よく栄養も考えられていると思います。
冷たい寒天はカロリーがないので、もちもちとして求肥をプラスすることで満足感があり、解毒作用のある小豆の餡と、ミネラルが多い干し杏…と、バランスがよい!
夏に甘いモノを食べたい時、干し杏を加えた「あんみつ」はおすすめです。
そして、パンやケーキを作るとき、干し杏を細かくカットして使うことで、とても美味しくできあがりますので、是非作ってみてくださいね。

製菓・製パン材料としても使う場合、一晩水に浸して柔らかくしてから砂糖を加えずちょっと煮込むと使いやすいでし、ジャムのようにヨーグルトに添えても美味しいです。
そして、ホットケーキミックスをカップに入れ、杏を入れるだけです。
何も料理をしなくても、そのままの状態で、紅茶のお供としてよく合いますが、紅茶の濃い目のアールグレイで煮込んだら美味しかった…と薬膳の生徒さんが言っていたので、様々な使い方があります。
甘いモノが食べたい方は、砂糖を加えた甘煮も作ってみてもいいですね。
<干し杏の甘煮>
- 干しあんず…200g
- 水…1カップ
- 砂糖…40g(甘さ控えめ)
- レモン汁…少々
※5分ほど煮るだけです。
干し杏の選び方

前述でも書きましたが、砂糖を加えて加工している干し杏は、砂糖は体を冷すので、健康を意識して食べる時は注意してください。
できるだけ、干してあるだけの杏を選んで、干し杏が持っている甘酸っぱさを楽しんでください。
そして、写真のとおり、鮮やかなオレンジ色をしている杏と、ほとんど茶色の杏があります。
外食先で食べる「あんみつ」の杏は見た目も大切であることから、食品添加物の漂白剤を加えて鮮やかな色にしています。
干しただけの杏は、鮮やかな色の杏より硬めであることから、これも食品添加物で調整しているものもあると思います。
お客様にお出しする食品は、色合いも大切なことがあるので、その用途に応じる必要がありますが、健康を意識して食べるのであれば、やはり無添加の方がよいと思います。
お料理の色合いが重要な場合の杏は、鮮やかな色のものを購入しています。

しかし、家庭内で料理するときは、小さな孫がいるので、砂糖も漂白剤(亜硫酸塩)も一切使用していないオーガニックもの選んでいます。
お気に入りのお店のタマチャンショップでは、様々な健康食材が売られているので、毎月何かしらを購入していますが、杏もお気に入りのひとつです。
杏(アプリコット)は、漂白処理をしていない有機栽培オーガニックで、爽やかな酸味とほんのり甘味を感じます。
砂糖を添加していないので、甘味がもっと欲しいと感じた方は、上記で紹介している甘煮にして食べると、おやつとして美味しくいただけると思います。
砂糖を使わず、漂白処理をしていない有機栽培オーガニック杏なのに、リーズナブル!おすすめ♪
料理をしなくても、間食のひとつとして干し杏は、おすすめです。
そして、街で杏を見かけたら「杏酒」を作ると、温活のひとつとして良いですよ。
毎日少しずつ食べると冷え性改善が期待できます。
↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1bd5aad4.d932e107.1bd5aad5.c7e15825/?me_id=1245590&item_id=10000213&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnuts-beans%2Fcabinet%2Fshyouhingyouho%2Fapricot_300g_a.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnuts-beans%2Fcabinet%2Fshyouhingyouho%2Fapricot_300g_a.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/154ca0cc.029b252a.154ca0cd.ea40f47a/?me_id=1208420&item_id=10020611&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkyunan%2Fcabinet%2Fdf%2F05499724%2Fimgrc0075991039.gif%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkyunan%2Fcabinet%2Fdf%2F05499724%2Fimgrc0075991039.gif%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1bd5b16a.2969c514.1bd5b16b.8285fb10/?me_id=1225639&item_id=10004848&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fokfruits%2Fcabinet%2Forganic-driedfruit%2Fimgrc0079041567.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fokfruits%2Fcabinet%2Forganic-driedfruit%2Fimgrc0079041567.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)