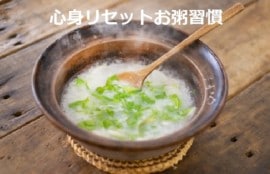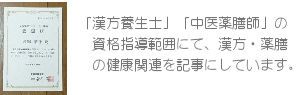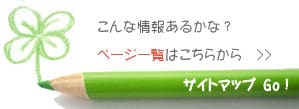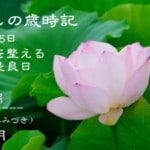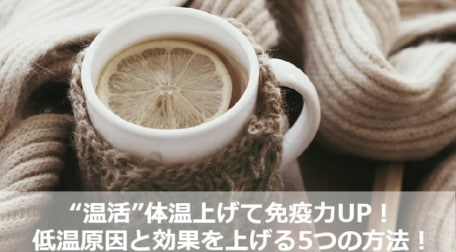Contents
八角・スターアニスとは?薬膳的解釈
「八角」というスパイスをご存知ですか?
西洋では「スターアニス」といい、料理本などでは様々な言い方をしているので、八角とスターアニスは別物と思っている方もいらっしゃるようです。
日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、中国やヨーロッパなどでは主要なスパイスのひとつとして親しまれています。
肉や魚のメイン料理から、デザートまでさまざまな料理に使われています。
八角(スターアニス)の味は、甘さの中に苦味が感じられるとても繊細で複雑な味でオリエンタルな雰囲気と奥ゆきを感じさせます。
独特の香りがするので、好き嫌いが分かれますが、中華料理の肉のおいしい料理と言われているものの中には、八角(スターアニス)が使われていることが多いです。
肉の毒や臭みを消し肉の消化を促進し、脂っぽい料理や肉料理に使うとさっぱりした印象になるので、料理で使ってみてください。
そして、香辛料としてだけでなく香水の原料として使われることもあるようです。
薬効も高く、漢方薬の材料や薬膳の食材として用いられます。
薬膳の解釈では、寒い時期“腎”が弱ってしまいますが、八角(スターアニス)には、気の巡りをよくして寒気を散らし、胃の調子を整え吐き気を抑え、痛みを止めるなどの働きがあるとされ、“腎”を補ってくれる食材としています。
冷え症の方や、生理痛や冷えによる腹痛、胃の調子が悪くて食欲がない時などに、料理のスパイスとして使ってみてください。
ウイルスや細菌から守る効果!風邪やインフルエンザ予防
八角(スターアニス)は、幅広い抗菌作用・抗ウイルス作用があります。
新型インフルエンザの薬の中にも含まれ、生薬として使われています。
八角(スターアニス)自体に、インフルエンザを治療する効果があるのではなく、抗菌・抗ウイルス作用・体をあたためるなどの相乗効果を狙ったものとして、薬に含まれています。
風邪の予防やインフルエンザにかかった時でも、八角(スターアニス)を使ったスパイス料理などで体を温め、抗菌作用を利用しましょう。
八角(スターアニス)の温活スパイス効果
寒いと感じられた時に“腎”を補うので、薬学書では腰痛や腹痛を改善したり、胃腸が弱ってしまい腹部膨張や吐き気や食欲不振、血行障害などの冷え性の治療、滋養強壮、新陳代謝を促すなどで八角(スターアニス)が使われています。
体が常に冷えている方の「温活スパイス」としておすすめで、同じ温活効果がある「シナモン」といっしょに使われることが多いです。

- 体をあたためる
- 痛みを止める
- 胃腸をととのえる
- 食欲を増進させる
- 気のめぐりをよくする
- 母乳の出を促進する
- ストレスを緩和する
効果が高いため、バクバク食べるモノではなく、香辛料などのような使い方をしてください。
八角(スターアニス)の使い方と食べ合せ薬膳

料理をする際、肉料理の味をつけたり、臭みをとったりするのによく使用されます。
肉の下味で八角(スターアニス)を1つ加えるだけでも、まろやかになって美味しく食べる事できます。
スープやカレーの隠し味などで、少量であれば気軽に使用できますね。
ケーキやドーナツ・クッキーなどのお菓子には、粉末状にして使用するのがおすすめです。
■風邪などの予防:柑橘系
煮だした八角(スターアニス)の汁に、金柑やみかんなどをプラスすることで、抗ウイルス作用に優れた八角にビタミンCが豊富な柑橘類が合います。
甘さを加えるのは、是非ハチミツを!
ハチミツにも抗菌作用がありますし、のどを潤してくれるので、風邪などの予防の抗菌作用や抗ウイルス作用が期待できます。
■コラーゲンたっぷり美肌効果:鶏肉
“気”を補い、コラーゲンがたっぷりの鶏の手羽先と、血の巡りをよくして温活効果があるので、八角(スターアニス)といっしょに煮込んでください。

ヨーロッパでは「スターアニス」と呼ばれ、シナモンと一緒に甘いデザートに使われることが多いです。
甘さと温かみのある風味を添えてくれるため、寒い季節に楽しむドリンクや焼き菓子に使われ、果物のコンポートや、焼きりんごなどにシナモンといっしょに使っても美味しいです。
インドなどでは、スパイスとして私たちの塩コショウと同じように料理に使われます。
薬膳では、体を温めてめぐりをよくするといわれている八角(スターアニス)は、体を温める温活としても使われ、痛みなどの改善も含め、生薬として使われます。
体に寒さを感じた時の温活、腹痛などの痛みの改善、そして風邪やインフルエンザ予防として、八角(スターアニス)を料理に取り入れてみてはいかがでしょう。
街のスーパーの香辛料の売り場で見かけられると思います。
↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日