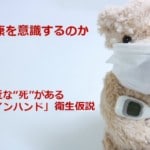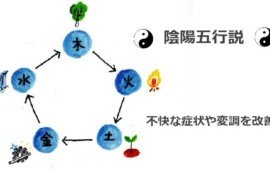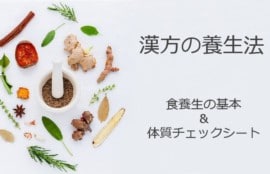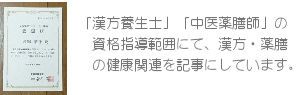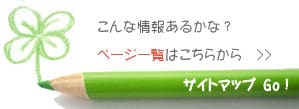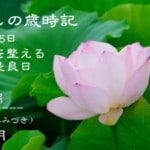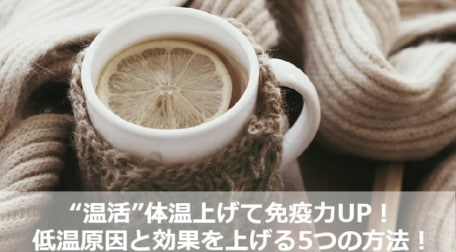体質のチェックシートで陰虚(いんきょ)が一番点数が多かった方のページです。
まだ体質チェックをされていない方は、ぜひチェックしてください。
↓
Contents
気滞タイプは気の巡りが悪くて精神的に不安定
体が元気であることを保つために必要な「気」「血」「水」の要である「気」の巡りが悪い状態です。
気・血・水の3要素バランスとは…
関連記事:不調の原因-気・血・水の3要素バランス
気の巡りが悪いというのは、西洋医学で自律神経の変化となります。
自律神経が失調してコントロールがうまくいかないので、イライラしたり怒りっぽくなり、逆に憂鬱になったり不安になって落ち込んだりしてしまいます。
気の巡りを司る臓器は「肝」で、気が流れる経路は体の両側あるため、流れが悪くなると体の両側に症状が出やすくなります。
オナラがいつもより臭くなったり、ゲップがいつもより多かったりします。
高血圧にもなりやすため、食事に気をつけましょう。
気滞タイプは気の巡りが悪い自律神経の不安定が原因・症状について

気の流れを司る「肝」の働きの強化が必要です。
お腹にガスが溜まっていることもあり、ゲップなど回数が多いようだったら、豆類やイモ類などをたべることを避けるようにしましょう。
顔が赤らんでいることが多く、血圧も高いことが多いので、リラックスすることが大切です。
自律神経のバランスを整える生活を意識しましょう。
| 症 状 | 原 因 |
|---|---|
|
|
気滞タイプの生活

どんな体質でも、疲労は先天的に持っている体質要素を悪化させてしまいますが、「気」の流れが悪いと、精神不安となり生活に支障をきたします。
昼は「陽」夜が「陰」と時間帯に陰陽関係があり、気滞タイプの方は特に生活改善が必要になります。
夜に起きて活動していると、寝ることで「陰」を養うのですが、夜間生活が続くことでダメージを受けやすくなるので、朝起きたら戸外の空気をいっぱい吸って深呼吸を10回ほどするなど、朝夜のメリハリがある生活をして自律神経を整えるようにしましょう。
何か問題があると落ち込んでいきやすいので、お風呂に入ったりしてリラックスする時間を意識してもつようにして、ゆっくり過ごしましょう。
自律神経を整え気の巡りを良くするためにも、お酒を飲む生活に気を付けて!
気滞がよくなる食養生
気滞タイプの人は、ストレスを解消する働きのある食材に意識しましょう。
ひと口に「気滞」症状と言っても、多岐に渡るため、それぞれの症状によって使う食材に注意が必要です。
ガスやゲップの多い人は、ガスが発生しやすいイモ類や豆を控え、香り野菜を多くとります。
冷え性の改善と鉄分・カルシウムなどを意識した血を増やす食材を食べるようにしましょう。

【気滞の食養生】
- 気の滞りを改善する「理気作用」香り野菜などを意識
- ガスやゲップの多い人は、イモ・豆などを避ける
- 香辛料の強い料理、辛すぎるものは避ける
【気滞改善の食材と注意】
- 平性・涼性の食材を使用
- 辛味の熱性の強い食材を避ける
- 甘味・酸味・苦味の食材を使用
- 肝を補う食材を使用
- 血圧を避ける食材
- 気の流れを促す薬味・ハーブ・スパイスを使用
【気滞タイプ:おすすめ食材】
- 漢方食材:陳皮・クコの実・菊花・ジャスミン
- 薬味:みょうが・こしょう
- 穀類&豆類:そば・発芽玄米
- 野菜&きのこ:ピーマン・トウモロコシ・オクラ・さやえんどう・キャベツ・レタス・香り野菜(春菊・セロリ・三つ葉など)
- 果物&木の実:もも・柑橘類
- 魚介&海藻:いか・くらげ・のり・ひじき・あさり・しじみ
- 肉・卵&乳製品:レバー
- 調味料:みそ・お酢
- 飲み物:ミント茶、ジャスミン茶、薔薇茶、ラベンダー茶
香り成分が多い野菜は、香りの精油成分に気の流れをよくしてストレスを解消するはたらきがあるので、長時間火にかけすぎないようにしましょう。
- レバー(牛:平性/甘味・豚:平性/苦味・鶏:微温性/甘味)「肝」の機能を整えて自律神経を安定させる
- イカ(微温性/鹹味)糖分の吸収を妨げるタウリンなどを含み「肝」の働きや血行をよくする
- あさり・しじみ(寒性/鹹味)体内の熱を冷まし、余分な水分を利尿し「肝」の調子を整える
- 苦瓜ゴーヤ(寒性/苦味)苦み成分に解熱・解毒・排毒作用があり、血圧の高い人や怒りっぽい人におすすめ
- 柑橘類(寒性・涼性/甘味・酸味・苦味)「肝」の機能を高め、抗酸化作用があり、リラックスできる
- 香り野菜(涼性/甘味)気滞タイプの頭痛に効果があり、イライラ解消や気の流れをよくする
- 梅干し(温性/酸味・苦味)健胃調整し消化機能を高め、「肝」をよくする酸味の食性がある
- クコの実(平性/甘味)「肝」「腎」の機能を高め、滋養強壮に良い
- 陳皮(温性/苦味・辛甘味)発汗・排泄を促し、腸内ガスを排出し、新陳代謝を高める
何を食べたらいいのか?…と悩んだら、「肝」を整える食材を中心に、よく噛んで食べましょう。
早寝早起きを習慣にして体内時計を整え、休息を十分にとって、適度な運動を心がけ、体のリズムと食のバランスに注意しましょう。
DNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日