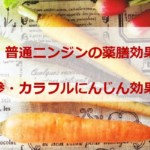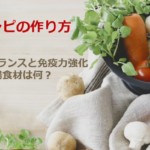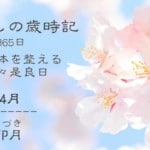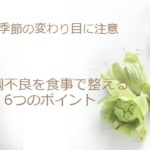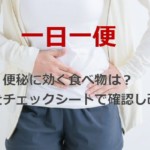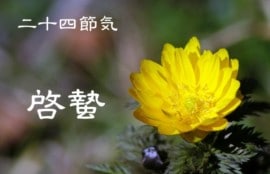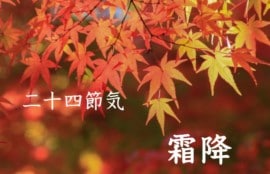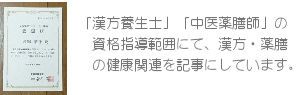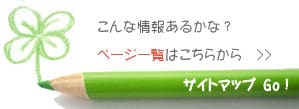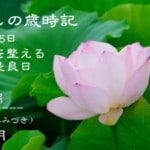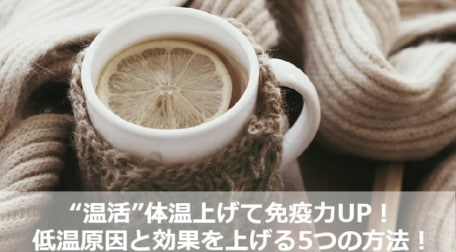Contents
二十四節気の秋【秋分-しゅうぶん】9/23~10/7頃:お彼岸
毎年9月23日頃を秋分の日と定められています。
「祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日」として1948年に法律で制定されました。
秋分の日は春分の日と同様、昼と夜の長さが等しくなる日で、お彼岸の中日にあたります。
春分の日よりも気温が10度程度高いですが、朝晩は過ごしやすくなってくる季節です。
真っ赤な彼岸花が道で見かけられ、お墓参りに行く方も多いのではないでしょうか。
実りの秋となり、山のきのこや野菜果物・海のサンマなど、秋に食べることで高い効果を得られますね。
乾燥のトラブルが多い秋!潤い食材を食べましょう
日本はもともと湿気が高い国なので、むくみやすいのですが、逆に乾燥して水分不足になると、体の対応力がないため治りにくいと言われています。
咳や気管支炎・ドライアイや肌トラブルと、乾燥系のアレルギー症状が出ることが多い季節です。
潤いを保つためには、潤滑油のような食材を食べるように心がけることが大切です。
空気が乾燥し始める秋に旬を迎えるなしは、肺を潤す効果が高い代表的な食材は、基本は旬のモノを食べることをおすすめします。
その中でも、効果が高く簡単に食べられるもの3つを紹介します。
のどの痛みや空咳、炎症、美肌効果など、潤い不足からくる便秘などにも効果が期待できます。
梨は乾燥した体を潤す食材

リンゴと梨が多く出回る季節ですね。
この2つの実を食べることがバランスの良い果物の食べ方です。
梨は約90%が水分で、甘くて咀嚼するとジュースのようになるので、そのまま食べても美味しいです。
梨に限らず、旬の食材を旬の時期に食べることで、その時の体に必要な栄養素を補うことができます。
梨の効能
- 利尿作用があるのでむくみ解消・二日酔いを軽減し毒素を排出
- せきや痰・のどの痛み呼吸器系の炎症を抑える
- コレステロール値の抑制して、高血圧の予防になる
- 便秘などなど、消化器系の働きを整える
- リンゴ酸、クエン酸、アスパラギン酸などで疲労回復になる
梨が大量にある場合は、ミキサーにかけてジュースにしたり、梨をすりおろしたものにレモン汁、塩、オリーブオイルを合わせたドレッシングもおすすめです。
梨は体を少し冷やす作用があるので、冷えがある方は生姜のすりおろしなど、体を温める食材と合わせて食べるようにするとバランスが取れます。
梨のドレッシング
 梨には甘みがあるので、甘味料が必要がないと思いますが、はちみつの殺菌作用を利用しています。
梨には甘みがあるので、甘味料が必要がないと思いますが、はちみつの殺菌作用を利用しています。
子どもが大好きな味だと思います。
<材料>
- 梨…80g
- 玉ねぎ…40g
- オリーブ油…大4
- レモン果汁…大1
- 酢…小2
- はちみつか砂糖(お好みの甘味料)10g
- 塩・コショウ適量
<作り方>
梨と玉ねぎを擦って、調味料を入れて混ぜるだけです。
白木耳(白きくらげ)はヒアルロン酸以上の保水力

“きくらげ”と言うと「黒きくらげ」のことを指す場合が多いですが、「白きくらげ」にも黒とは違った素晴らしい効能があり、薬膳では黒きくらげよりも薬効があるとされています。
世界三大美女として有名な楊貴妃も、不老不死を願って「白木耳」を常食していたと言われています。
体の内側から乾燥肌対策に取り組みたい…という方に、一番おすすめしたいのが白きくらげです。
白きくらげには味や香りはほとんどなく、喉などの粘膜をやさしく労わってくれます。
白きくらげにしか含まれない「白きくらげ多糖類」という成分は、ヒアルロン酸以上に保水力があるとされているので、乾燥肌対策やアトピーなどのカサカサのかゆみの軽減になります。
白きくらげは無味無臭なので、スープやサラダと様々な料理にアレンジしやすく、乾燥状態で売られているので、ストックできるのも便利です。
食べる美容液:梨と白きくらげのはちみつコンポート
粘膜や肌を潤す「白きくらげ・梨・はちみつ」を組み合わせたデザートは、体内を潤す組み合わせなので、秋などの外気の乾燥する季節などにもおすすめです。

<材料>
- 梨…1/2
- 白きくらげ…6~10g
- はちみつ 大さじ2〜好み
- 水適量
- レモン汁 お好み
<作り方>
- 白きくらげはたっぷりの水に30分ぐらい浸けて、硬い部分は取り除いて食べやすい多きさにちぎります。
- 梨を一口サイズに切って、鍋に梨と白きくらげを入れてひたひたになるまで水を入れ煮ます。
- はちみつを加え、沸騰したら中火にして水気が少なくなるまで煮込んで、仕上げにレモン汁をかけてできあがり。
- 冷蔵庫で冷やしていただくと美味しいです。
白きくらげのホタテ薬膳スープ
貝柱の栄養価は干し貝柱にすると凝縮され、貝柱部分には100g当たり420㎎と魚介類ではトップクラスのカリウム含有量があり、デトックス効果があります。
干し貝柱は漢方薬としても疲れていて、滋養強壮・血圧降下・肌のうるおい・めまい改善・のどの渇き改善などの効果があります。
菊には解毒作用があり、体のなかにある解毒物質「グルタチオン」の産生を助ける成分があるので、添えました。
クコの実はドライアイや眼精疲労にもよく、「食べる目薬」ともいわれています。
クコの実;リンク

<材料>
- 白きくらげ
- 貝柱
- 春菊
- かぶ
- ネギ
- しょうが
- クコの実はお好み
- 水
- 無添加鶏ガラスープ
- 酒 少々
- ゴマ油 好み
- ゴマ少々 好み
- 塩・コショウ 少々
<作り方>
- 干し貝柱の戻し汁は、できものや腫れものにも効き目があるので、干し貝柱はサッと洗って鍋に入れます。
気になる方は、水で戻してください。 - 白きくらげは水に20分ほど浸けて、戻します。
- 鍋に飲みたい量の水に、貝柱と白きくらげを無添加鶏ガラスープの素を加えて煮込みます。
貝柱が柔らかくなってきたら、ネギと春菊を加え、酒や塩コショウで味付けをします。 - 好みでごま油やゴマを加えて、仕上げにクコの実を入れてできあがりです。

秋の美肌スムージー
 「水分やミネラルを補う牛乳に、お肌の潤い目的のスムージーです。
「水分やミネラルを補う牛乳に、お肌の潤い目的のスムージーです。
牛乳と豆乳を混ぜなくてもどちらか一方でもOKです。
血を補いうるおい成分をアップさせる黒ゴマと、お肌に潤いを与え、夏の疲れを引き延ばさないように加えました。
肌のカサカサ・貧血・血色の改善・目のかすみ・便秘など、秋の悩みを解消します。
<材料>
- 黒ゴマ…大さじ1
- きなこ…大さじ1
- 黒砂糖(好み)…大さじ1
- 牛乳…200cc(豆乳でもOK)
<作り方>
ミキサーに材料を入れ、なめらかになるまで撹拌するだけですし、ミキサーを使用しなくてもOK!
良質なサンマや、果実や野菜は冬の体づくりを助けてくれます。
キノコは冬に耐える免疫力をつけてくれます。
旬のものを食べることで、自然にその季節にあった効能がありので、実りの秋の旬を楽しんでくださいね。
東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日