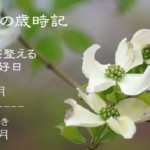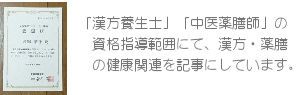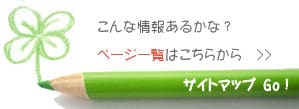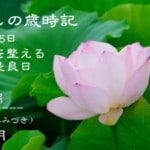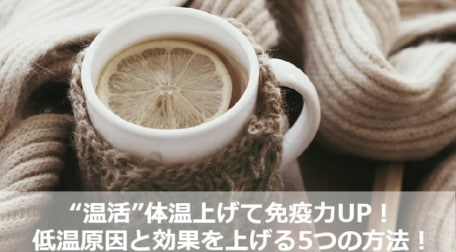七色健康食事法基本ページ
Contents
7色食事療法で細胞力を強くしよう!
健康のために野菜を1日300~350gを摂り、そのうち1/3は緑黄色野菜をとるようにと、栄養学の角度からは言われていますね。
緑と黄の野菜を合わせて1/3なので、大量に食べなければならない野菜ではありませんが、毎日とることが必要です。
緑の食材で思い出せるのは、ほうれん草や小松菜・青梗菜やブロッコリー、果物ではキウイなどすぐに思い出せる野菜が多いです。
光合成をおこなう鮮やかな緑色に変化する“クロロフィル”を含む緑色食材は、ガンを予防したり血液の循環を助けてくれます。
食事が美味しそうにみえる視覚的なものも、緑の野菜は必要です。
緑の食材は野菜でも多くありますが、緑茶も緑色野菜になります。
緑の食品パワーの食材と働き

多くの野菜が緑色をしているのはファイトケミカルのひとつ「クロロフィル(葉緑素)」が関係していて、光を浴びて光合成を行うことで鮮やかな緑に変化しています。
クロロフィルを含んだ野菜は、抗酸化作用や抗がん作用を持ち、酸素や血液の循環を助けて貧血の予防をしてくれます。
そして、β-カロチンも含まれ、体内でビタミンAに変換されて抗酸化作用を発揮してくれるのです。
【緑の食材】
- ほうれんそう…遺伝子の傷つきを防ぎガン予防をし、紫外線から身を守り皮膚がん抑制効果。
- 春菊…香り成分に殺菌作用があり、病原菌をストップさせる。
- ピーマン…カロテンとビタミンCが壊れにくく、活性酸素から遺伝子の損傷を防ぐ。
- にら…色素と匂い成分が細胞のガン化を阻止し、活性酸素を無毒にする酵素の重要な構成成分。
- グリンピース…細胞を生成するときの栄養が豊富で抗がん作用がある。
- 枝豆…脳の神経伝達物質の合成に欠かせないレシチンを含む。。
- キウイ…ポリフェノールのタンニンの抗酸化作用が期待できる。
- 緑茶…ポリフェノールのカテキンは抗酸化作用があり、発がん・動脈硬化予防に有効。
- レタス…あまり栄養価が高い野菜ではないが、ビタミンEは細胞の老化を防ぐ。
- きゅうり…β-カロチンが豊富で体内の細胞を若々しく保ち、カリウムが多いことから、利尿作用もあります。
- アブラナ科(キャベツ・ブロッコリーなど)…発がん性物質の解毒作用を活性化させ、消化器系や肺などのガンを抑制。
…など
習慣化して食べる「緑の食材」

主菜に対比して必ず添えて欲しいのが、緑の野菜です。
アブラナ科であるブロッコリー・キャベツなど、野菜全体の1/4を占めるものですが、共通に含まれるイオウ化合物に発がん抑制作用があり、特にイソチオシアネートは発ガン物質の解毒酵素を活性化してくれます。
その働きによって、食道・大腸・肝臓・肺などのガンを抑制し、カロテン・ルテイン・クロロフィルなどの色素成分が多く含まれています。
緑の野菜に含まれている葉酸は細胞の新生に不可欠で、更に傷ついた遺伝子を修復するという抗がん効果があるのです。
レタス・キャベツ・きゅうりなどはサラダと食べることが多いと思います。
量を食べるために、ビタミンは流れてしまう可能性がありますが、炒めたり茹でたりして食べる方法も必要になります。
ビタミンCはビタミンEである油で炒めると栄養アップします。
この食材が黄色?…と悩むような食材
この食材は何色?と悩むような食材もあります。
食材の色は基本、食べる部分や大部分をしめる部分から判断するのですが、キュウリやズッキーニの場合、皮が緑で食べる部分は白ですね。
しかし、白い部分よりも皮の緑の部分に栄養が多く含まれていることから、緑に属しています。
果物のキウイは皮が茶で剥いて、緑の実を食べるため緑です。
マメ科でも大豆は茶色ですが、枝豆は緑色と別れますが、黒豆は黒であることから、見た目のままの色分けとなります。
体の機能を整える働きのあるミネラルやビタミンをたっぷり含んだ緑色の野菜は、食事毎に食べるように心がけましょう。
七色健康食事法基本ページ
↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日