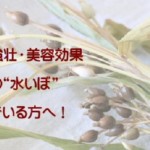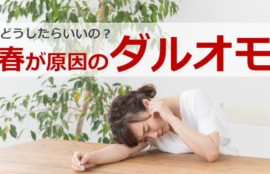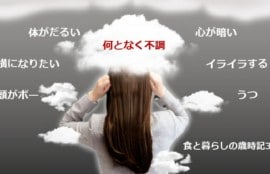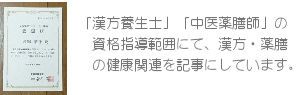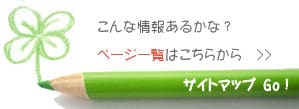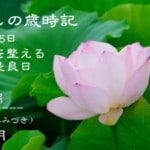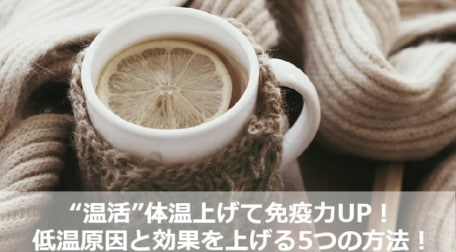我家は家族が多いのでお餅が大量に必要なため、お餅つき機でお餅を作ります。
健康のためにヨモギ餅や吉備餅などをつくりますが、今回は白いお餅の食べ時や体によいトッピングの紹介をします。
Contents
鏡餅は年神様の力が宿っている

餅は古くから神様の食べ物と言われ、歳神様へのお供え物です。
歳神様が帰ったあとの鏡餅には、歳神様の力が宿っているので、そのお餅を食べることで歳神様の力を授けてもらいます。
無病息災を祈り感謝するというのが鏡開きの目的です。
食べる時は包丁を使わないで小槌で叩いて割ります。
「割る」という言葉は縁起が悪いとされ、「開く」という言葉が使われています。
お餅は“力”がつくって本当か?
お餅を入れたうどんを「力うどん」と言いますが、腹持ちがよくて力がでるから、という意味があります。
お餅には炭水化物が多く含まれ、炭水化物の要素のひとつである「糖質」は、体内でブドウ糖に変わるから、体を動かすためのエネルギーになり、腹持ちがよくなるのでしょう。
昔からよく「餅は持久力がつく」と言われ、お餅の粘り気が腹持ちを良くします。
手軽に多くのエネルギーを摂取することができることから、スポーツ選手に好まれています。
お餅の原材料“もち米”について

お餅の原材料は「もち米」です。
もち米はお祝い事の時によく使われ、「お赤飯」はなじみ深いのではないでしょうか。
昔は、保存食としても重宝されてきたもので、現代でも長期保存ができる優れものですね。
もち米は、米よりも気を補う効果があり、全身のいたるところを流れるエネルギーを補う効果が高い食材です。
疲労回復、慢性疲労、胃の調子を整える、下痢、頻尿、咳止めに効果的と言われていますが、太るのではないか?と心配される方が多いです。
しかし、基本の気が不足すると脂肪がつきやすくなり、筋肉がつきにくく筋力が弱いという事態を招きます。
気が不足すると体が下垂して、下半身がぽっちゃりしてきます。
もち米は、普段の食卓に適度に取り入れて、気を補うことをおすすめします。
結果、気を補うのでダイエットにも役立ちます。
もち米の薬膳的効能
- 補気…体の気を補う
- 五性…温性(体を温める作用がある。)
- 五味…甘味(緩和と滋養強壮作用・脾、胃によい。)
- 帰経…脾臓、胃、肺に作用する。
お餅の効率の良い食べ方

中医学的に見ても、「脾」である消化器系の働きを高めて、胃を温めてくれる効果があり、慢性的な疲れの改善には良いとされています。
体を温める力があるため、冷えからくる下痢にも有効ですが、どんな時でもよいのか?…というと、そういう訳ではありません。
例えば、夏バテ。
夏バテは「食欲がない上に、疲労感がある」という症状があります。
そのようなときは、ちょっと注意!
「食欲がない。胃の調子がよくないかも…」というときは、もっちりとしたお餅よりも、雑炊などで消化器に負担をかけないようなお粥や雑炊などを食べるようにします。
「食欲がある…そして、胃腸の調子も悪くない」しかし、活力がないと感じられるとき、お餅を食べると効率よいのでおすすめです。
そして、
お酒といっしょにお餅を食べてしまうと、酔いが解消しにくくなるので、お酒の〆にお餅は避けるようにしましょう。
体に良いお餅のトッピング5つ
代表的なお餅の食べ方が、健康にもよいので、その効能を紹介します。
おしるこや黒ゴマなど甘くしたい方は、甘味料にオリゴ糖が多い「てんさい糖」や、ミネラルが多い「黒砂糖」を使うようにした方が、効果がアップします。う。
きな粉をトッピング:腸内環境を整えて肥満抑制効果

きな粉の食物繊維の量は、大さじ1杯で豆腐3丁分あるので、腸内を整えるにあたり、効率がよい食材です。
そのきな粉をお餅にトッピングすることで、血糖値の上昇を抑えて、肥満を予防できます。
焼いたり茹でたりしてやわらかくしたお餅に、甘味料を加えたきな粉をかけるか、甘味料を加えないきなこに、黒蜜をかけても美味しいです。
チーズ(プラス海苔)をトッピング:骨の強化

骨を丈夫にするチーズのカルシウムが、牛乳の5~10倍含まれています。
骨を強くするには、カルシウムとたんぱく質が必要で、そのバランスが良いのがお餅とチーズ。
お餅とチーズに海苔添え、発酵食品の醤油で食べることで、栄養効果がアップします。
焼いたり茹でたりしてやわらかくしたお餅に、チーズをのせ、海苔をかけたり巻いたりします。
大根おろしをトッピング:肝臓の解毒作用を助ける

大根に含まれるビタミンCが肝臓の解毒作用を助けてくれますが、大根の皮に多くのビタミンCが含まれているので、皮をむかないで食べましょう。
お餅にはパントテン酸が含まれ、ビタミンCといっしょに摂ることでビタミンCの働きを助けてくれます。
パントテン酸とは、様々な栄養素をエネルギーに変換するために、脂肪の蓄積を予防してくれます。
大根おろしは食べる直前に擦って、すぐに食べないと効果がありません。
小豆をトッピング:体のむくみを取り除き、老化、ガンを予防

小豆の煮汁には、体のむくみを取り除くカリウムと、老化やがんを予防するサポニンが含まれていて、ビタミンB1・B2・ポリフェノールなどが豊富です。
1月15日の小正月でも小豆を使用した食事が多く、日本の祭事では小豆は多く使われ、昔から小豆には不思議な力があると大切に栽培されていました。
お粥に小豆を入れたり…と、もらすことなく、お餅に小豆をトッピングするのは、体を良い方向に導いてくれます。
煮汁に栄養があるため、おしるこ・ぜんざいがおすすめ!
黒ゴマをトッピング:貧血や生活習慣病予防

黒ごまに含まれているセサミン・アントシアニン・ビタミンEには、抗酸化作用があるので、動脈硬化など様々な生活習慣病予防になります。
不飽和脂肪酸が多く含まれているので、血栓の生成を抑制したり、LDL(悪玉)コレステロールを減少させるといった働きがあるからです。
貧血気味の方には、1日1食に黒ゴマを使うことをおすすめしていますが、黒ゴマには赤血球の生成に必要な、鉄、葉酸、ビタミンB12などが多く含まれています。
力をつけたい!プラス効能を生かすお餅の食べ方

ダイエットをしている方にとって、お餅は天敵のようにされがちですが、お餅1個を食べることで、効率よくエネルギーを取るひとつの食材です。
そして滋養強壮など、体に“力”をつけたく、更にトッピングによってさまざまな効能が期待されます。
お餅は災害時の保存食としても、昔からストックされていたもの。
常にお餅をローリングストックしておくことで災害時は安心ですし、疲れた時に簡単に食べることができるお餅は、おすすめです。
↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日