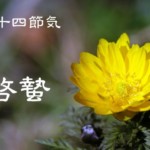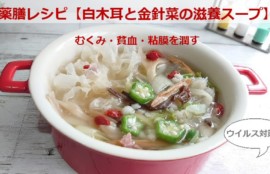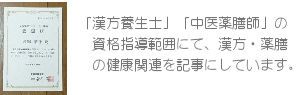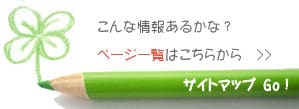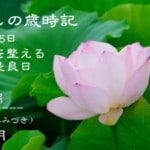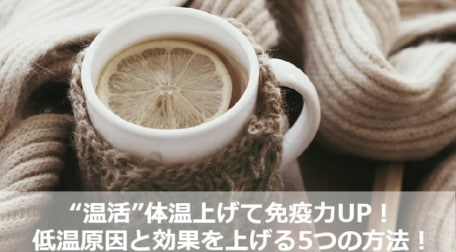中華料理で使われるミックス調味料といえば五香粉(ごこうふん・ウーシャンフェン)
材料に使われている香辛料は、どれも漢方の生薬になっているものです。
そんな漢方薬のような「五香粉」の効果と、もっと身近な調味料としての使い方を紹介します。
Contents
五香粉とは?(ごこうふん、ウーシャンフェン)

五香粉は、中国料理に使用される代表的な香辛料の1つで、そのひとつひとつの香辛料はどれも生薬になるものです。
5種類のスパイスが含まれた複合調味料と思われがちですが、実際は五香粉の五とは「多い」「複雑」などの意味があり、五香は“数種類の香”ということなので、厳密に5種類と決まっているわけではありません。
中国の代表的な混合香辛料(ミックススパイス)の「五香粉」は、様々な配合がありますが、丁香( クローブ )・桂皮(シナモン)・花椒(ホアジャオ)の3種と、陳皮(チンピ)・大茴( 八角 ・スターアニス)・小茴( フェンネル )のうち2種を使い、合計で5種類が混合されるのが一般的になっています。
中国料理を中心に、シナモンやスターアニスなどから醸し出される甘くエキゾチックな香りが特徴のベトナムやインドシナ地域でも使用されています。
五香粉は、炒め物や揚げ物の味付けなどに少量を料理に入れるだけで中華系の味になるので、中華料理には欠かせません。
中華料理の調味料「五香粉」の各種材料の漢方効果

五香粉(ごこうふん、ウーシャンフェン)は、料理にも健康にもとても重宝する調味料で、誰もが気軽に使える漢方薬のようです。
混ぜ合わせてあるそれぞれの単品香辛料の効果と、調合されていることで得る漢方効果について、紹介します。
五香粉(ごこうふん、ウーシャンフェン)は、配合されるスパイスが異なります。
自分の症状に合わせて、他の調味料をプラスしたりと、自分の体調や味の調整もできます。
五香粉の基本は、4つの香りスパイスと1つの辛みスパイスで出来上がる「四香一辛」とされていることから、花椒は辛みスパイスとして中国のほとんどの地域で使用されています。
花椒(ホアジャオ)
日本料理では山椒…中華料理では「花椒」と、同じミカン科サンショウ属の落葉低木ですが、痺れが強い「花椒」は、辛みの香辛料として五香粉には必ず配合されています。
体内の余分な水分を取り除き水分代謝を改善し、お腹を温めて冷えを改善する「温中散寒」の効果があります。
古くより回虫による腹痛・嘔吐などの殺虫止痛作用の効果があるので使用され、殺菌や鎮痛としての麻酔効果を利用されてきました。
関連記事にて、効能を紹介しています。
陳皮(チンピ)
みかんの皮を乾燥しただけなのに、ペクチン・フラボノイド・クエン酸を多く含み、漢方では良く使われ、風邪に効き胃腸薬や体を温める効果があります。
香りもよい陳皮は効果・効能は、毛細血管の強化や血流の改善で体を温め、生活習慣病の予防・改善効果などとても多く、食生活に取り入れたいです。
栄養や香りもあり、紅茶に入れたりぬか漬けにいれてもおいしくなります。
関連記事にて、効能を紹介しています。
桂皮(シナモン)
桂皮は、7割近く漢方薬の処方として使用されている優れものです。
消えた毛細血管を再生させる上、胃腸を温め、消化機能を高めてくれる「温脾胃」の効果があります。
冷え性の体を温めて機能を高める「暖肝腎」効果や、体内に入っている水分を出す働きがあり、ドリンクやお菓子など、幅広く使える調味料です。
関連記事にて、効能を紹介しています。
丁香( クローブ )
胃腸の働きをよくする漢方薬で、植物の中で一番抗感染作用、抗菌特性があるほか、カビの増殖を抑える“抗カビ特性”もあります。
腎の機能を高め、体を温める機能を回復させる「補腎助陽」効果があり、歯痛剤としても使用されます。
関連記事にて、効能を紹介しています。
小茴( フェンネル )
抗酸化作用があるので、毎日の食事に取り入れることで免疫力アップにも役立ちます。
動脈硬化の予防のために、毛細血管を保護や血圧を正常化させ、胆汁の分泌を促して、消化促進作用・鎮痛や鎮静作用などの効果があります。
血行が促進されることで体内の巡りが良くなり、冷え性の改善や利尿・発汗作用がはたらき、むくみの改善なども期待できます。
関連記事にて、効能を紹介しています。
大茴( 八角 ・スターアニス)
温活欠かせない大茴は「八角」と言う方が馴染みがあると思います。
胃腸を温め機能を回復する「温陽散寒」の効果があることから、胃腸の働きを活発にし、新陳代謝を高める薬用にも使われています。
ウイルスや細菌から守る効果・風邪やインフルエンザ予防などのかぜ薬にもなり、気の巡りを良くし、痛みを止める「理気止痛」にも使われています。
石けんや歯みがきなどの香料としても用いられていますが、基本的には中華料理の香り付けとして使用されています。
関連記事にて、効能を紹介しています。
五香粉の総合的な漢方効果

前述では五香粉に使用する香辛料を6種類紹介しましたが、五香粉はメーカーによって配合が違うため、味も違ってきます。
しかし、漢方効果の目的とする方向性は同じで、「辛温の性質をもっていて、胃腸を温め消化を促進する効果」が得られるような生薬です。
五香粉で調理した肉を食べると、胃腸が強い人は、食べ過ぎても新陳代謝が促進され肥満予防効果が期待でき、肉類が食べられない胃腸が弱い人は、お腹を壊す確率が減る可能性が高くなります。
湿気が多い梅雨の時期は、胃腸の機能が弱くなりますが、五香粉の温め効果でお腹を壊しにくくなります。
中華料理でコッテリした料理に使われやすいのは、油で冷えた胃腸を温め守るためにあるような、漢方薬をギュ~と配合した香辛料を、調理で使用することで、体を整えることができる優れた調味料です。
五香粉はどのような料理に使用するのか
五香粉は、独特なスパイスの香りを持っている上、抗菌作用も兼ね備えているので、肉や魚の生臭い臭みを消すのに効果的です。
鶏肉の唐揚げの味付けや臭い消しに「ニンニク」をよく使うと思いますが、ニンニクの代わりに「五香粉」を使ってみると食後の口臭も気になりません。
塩コショウと五香粉を混ぜ合わせてから揚げを作ってみると、中華風から揚げになります。
炒め物でも、仕上げに食卓の上でパッパとひとふりかけて食べる方法もあり、魚の蒸し煮にもよく使用され、チャーシューなどを作るときも、ちょっと使用するだけで、風味がかわります。
台湾ラーメンにも味の決め手のスパイスとして「五香粉」が使われていますし、実は外食先でも多くの五香粉を使用した料理を食べていると思います。
中華のお菓子などでも、スパイシー風なパウンドケーキに五香粉が使われていることもあります。
五香粉は中華料理には欠かせない香辛料で、料理のアクセントに最適です。

日本で売られている五香粉でも、様々な味の違いがあります。
それは使っている材料は同じでも、配合比率が違ったり、使用している材料そのものも違います。
原材料は、使用した重量の割合の高い順に表示されています。
- ハウス食品「GABAN」の商品表示「原材料」は、八角・花椒・シナモン・陳皮・クローブ
- エスビー食品の商品表示「原材料」は、スターアニス(八角)・シナモン・花椒・クローブ・陳皮
食べ比べてみると、配合の違いで味に違いを感じ、エスビー食品は、シナモンの味をとても強く感じました。
生薬が使用されている「五香粉」は、健康維持に効果の高いものを取り入れる「薬膳料理」でもよく使用されます。
漢方の生薬をそのまま取り入れると、「臭い」が嫌いという人が多いですが、調味料として生薬を粉に加工されて配合されている香辛料を、毎日の料理に応用して取り入れてみてはいかがでしょう。
単品で様々な効果効能を考えて料理するのが大変という方は、中華料理では健康を維持するために「五香粉」を取り入れることで、食べやすくなります。
料理のアクセントとして使用するのも美味しいですが、健康の事を考えても是非取り入れたい調味料のひとつです。
↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。
DNAフードゆるラボ 関連記事
最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)
- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日
- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日
- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日